他人の夢の話が嫌いなひとは読まない方がいいと思うのです。
今日は寝床に見る夢の話だから。
ただ自分は、知人から聴くものも含めて夢の話が好きです。夢の中では理性や常識から驚くほど自由になって、気狂いなのではないかというような、予期しない展開が簡単に起きるというのもありますし、会ったことがない人が突然出演する不思議もあります。
今朝方の夢は、美容院に就職するという夢で始まりました。
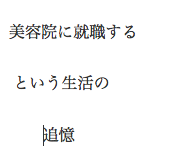
面接とかではなくて、すでに就職が決まった初日で広い院内を案内してもらうという出だし。
美容院の方とは旧式の電話ボックスで待ち合わせをしました。そして、これから院内へ向かうのですが、古いコインを入れて使うタイプの電話を何故かワンタッチで取り外して持って行くことになっているようでした。
もちろん新人なので、取り外した電話は私が持ちます。
歩いて直ぐの所に美容院がありました。とても広い建物のようでガラス張りの大きな窓の側には水草の浮く池まであります。見覚えのない顔のスタッフが六人くらい働いています。そこを大きな電話を抱えたまま順々に挨拶して回るのですが、頭のなかでは「今更むりだよな〜、ここでは働けないよな〜」と思っています。
そして、全員に挨拶が終わると、白くて天井の低い長い廊下を担当者に連れられて二人で歩いていきます。
突き当たりには、やはり同じように白くて、割りと立派な模様入りの扉があります。担当の方が扉を開け、中に入ります。
すると、
そこには壮大な石造りのハマム(トルコとかアラブにみられるお風呂のスタイル、サウナ式浴槽)が突然現れました。
天井は10mくらいの高さで全て石造り、所々に石柱が立ち、カーブには同じ石で誂えたベンチのような長椅子が設置されて高級なスパのようになっています。中央にも日の光りがそこだけ当たるように設計された石段があり、至る所に半裸や全裸、タオル姿の人々が寝転がったり談笑したりしています。
うっすらと霧のようにこもった湯気や白い石、高い天井からさす自然の灯り、それらがあいまって醸しだす雰囲気はローマ時代か何かのような、なんとも壮厳な印象を与えます。
担当の人が浴室支配人に「新しく入った新人に施設を紹介する」と断りを入れて奥の方へ進んで行きます。
左の壁と床の一部がガラス張りで、その向こうは地下鉄駅のプラットホームになっていました。東京のどこか忙しい駅で、沢山の人が電車を待っていますが、向こうからこちらは見えないようでした。
お風呂の中にこんな窓があるものか、と驚愕しながら先へ連れて行かれると、通路が急カーブして薄暗い一角に出ます。地下なのだと思われる通りですが雰囲気は昔の1930年ごろのフランスで、当時の帽子を被りロングコートを羽織った浮浪者か酔っぱらいらしき男が石畳を歩いています。
担当者はいつの間にか、昔働いていたレストランの店長さんに変わっていて、その人が通路のある壁を押すと、そこは隠し扉になっていて地下へと続く道が始まりした。
雰囲気はどことなくディズニーチックで、少し笑えるようなちゃちな感じを受けました。
店長はその道の途中で、用意された剣のような長物を拾いあげ何かをやっつけるような仕草で走っていきます。後ろから物騒だなと思いながら付いて行くと、急に視界が晴れる一角にでました。
「ダメだ、時間切れだ」
店長は残念そうにそう呟くと剣を下ろしました。多分ボスキャラ的な敵をバッサリとやるつもりだったのでしょうが、誰もいなかったのです。
開けてやや明るくなった一角には他にも剣を持って到着した二人組が何人かいて、上を見上げると二階はゲームセンターになっていました。そこでは、まるで競馬のコインゲームに賭けるように僕らの到着を待っていた人がいて、喜んだり、「ダメだ」とか呟いたりしています。
どうやらいつのまにか賭け事のレースに出場していたみたいです。店長がボスキャラを倒せば喜ばれたのでしょうが、僕たちは時間切れで間に合わなかったのです。
「なんだよ、ゲームかよ」
そう思って辺りを見回すと小舟が、それもディズニーの施設内で使われていそうなちゃちな小舟が何艘か流れてきたのでした。
それで夢はおしまい。
荘厳なハマムにただよっていた湯気の余韻を引きずったまま瞼を開きました。
豪華で貴族的なあの美容院から浴場までの流れは、先日読み終えた「ドリアン・グレイの肖像」という小説の影響があったと思う。美容院やローマ風呂が小説に直接出て来るわけではないけれど、なんとなく薄暗く豪奢な世界は通ずるところがあったのです。
著者であるオスカー・ワイルドがヘンリー卿という貴族に語らせた言葉で今日は幕引き。
きみは自分を安全と信じこみ、強き人間と考えているかもしれないが、しかし、部屋のなか、あるいは朝空のなかにふと認められた色あい、昔好きだったために、いまでも嗅ぐたびに妙なる思い出を匂わせる香水、かつて眼にふれたことのある忘れられた詩の一行、弾くことをやめてしまった曲の一節──いいかい、ドリアン、こういったものにこそ、人間の生活は左右されているのだ。
オスカー・ワイルド「ドリアン・グレイの肖像」新潮文庫